特集
公器の理念から生まれる未来:
岡田卓也がつくったイオンと、公益資本主義の可能性
「公器の理念が支えた静かなる流通革命」と向き合う
私が、「公器の理念」という日本の商人の思想に関心を持つようになったきっかけは、石井淳蔵先生の著書『岡田卓也の時代: 公器の理念が支えた静かなる流通革命』(碩学舎、2024年)の出版である。同書は、その副題に示されているように、岡田卓也氏が公器の理念のもとで、流通革命の時代において独自の事業展開を果たしていった経緯を描く。
『岡田卓也の時代』がとらえているのは、1946年に岡田卓也氏が経営者となった岡田屋が、ジャスコ、イオンへと発展を遂げていく歩みである。そこから見えてくるのは、伝統的に日本の商人が大切にしてきた精神、あるいは理念を引き継いだ岡田卓也氏と岡田屋が、日本の近代流通システムの大転換期にいかに挑み、そこからどのような経営のあり方が生まれていったかである。この書籍は、三重県四日市の一商店だった岡田屋が、期せずして直面することになった流通革命の荒波に対峙するなかで、日本の商人の理念を守りながら独自の経営を展開していった足跡をたどる。
流通革命の時代のなかでの挑戦
『岡田卓也の時代』の縦糸は、流通革命の時代に前後する小売のビジネスモデルの動態であり、横糸はそこで経営の精神が果たしていた役割である(図1)。1960~70年代の日本では大量生産・大量消費社会への転換が都市部から全国へと広がっていき、流通システムも大きな変貌を遂げていった。流通戦国時代ともいえる状況のもとで、「問屋不要論」が唱えられ、伝統的な流通経路の再編が進んだり、台頭するスーパーマーケットなどが、買い物行動をはじめとする家庭の日常を変えたりしていった。
この時代の流通産業の旗手として、多くの方が想起するのは、中内功氏のダイエーであろうか。あるいは堤清二氏のセゾンだろうか。その一方でジャスコは、相対的に静かな存在だった。すなわち、ジャスコは新しい時代の小売経営に積極的に挑戦していたものの、全国的には一番手といえる存在ではなかったのである。
なお、ジャスコが「静かなる流通革命」の担い手だったというのは、当時のダイエーやセゾンなどと比較した場合の話である。岡田屋からジャスコへの歩みは、同社の内から見れば、『岡田卓也の時代』のなかで活写されているように、坂道を息を切らして駆け上がっていくような日々だった。岡田卓也氏は流通近代化の道を開くべく、合併などを重ねていき、そのなかで他者とのつながりに伴う責任などにていねいに向かい合いながら、独自の歩みを展開していった。
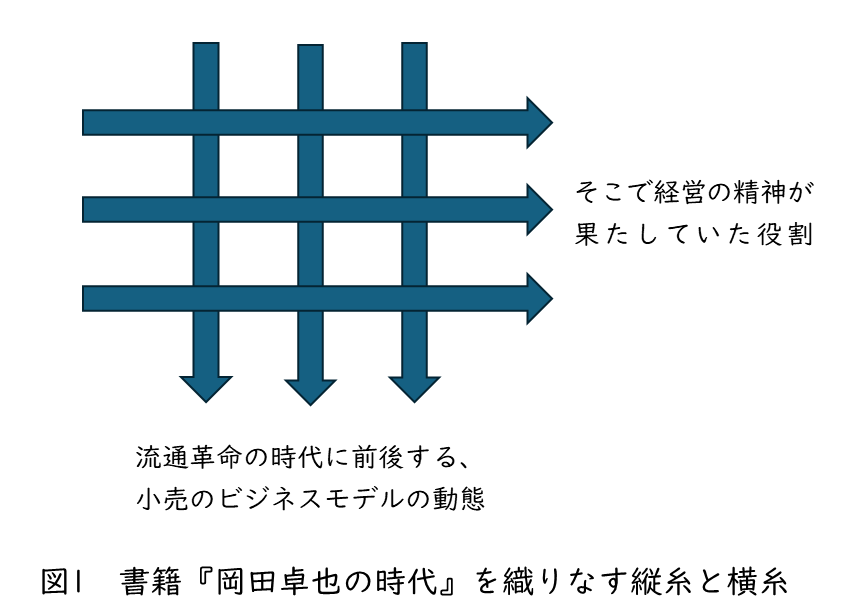
「静かなる流通革命」の到達点と、公器の理念が果たした役割
ビジネスの世界は変化が絶えない。一世を風靡したビジネスモデルも、時間がたてば輝きを失う。現在、私たちの目の前に広がる光景は、かつてのそれとは大きく異なる。流通革命は遠いかなたの出来事となり、当時、時代の旗手と賞賛されていたビジネスモデルが、今では次々と退場を余儀なくされている。
岡田屋にはじまるジャスコとイオンの歩みは、短期決戦ではなく、中長期の展開のなかでその強みを発揮していったといえる。現在、イオンはかつてのような二番手、三番手の存在とはいえなくなっている。現時点での営業収益は、確かにセブン&アイを下回っているが、セブン&アイの営業収益の四分の三は海外のコンビニ事業によるものである。また、セブン&アイは今後、総合スーパーや外食などの非コンビニ事業を分離していくことを発表している。このようなことからイオンを国内で最大の小売グループと見なしても問題はないだろう。
現在のこのポジションは「静かなる流通革命」の一つの到達点だといえるだろう。「静かなる流通革命」が、公器の理念を反映したものであったことは、『岡田卓也の時代』が描く通りである。では、この静かなる流通革命における公器の理念が、現在のイオンへと至る道のりにおいて果たした役割は、どのように読み解けばよいのか。
この問いに答える鍵は、公器の理念を短期決戦ではなく、中長期の事業継続のための処方箋と見る理解だろう。岡田屋、そしてジャスコからイオンへと至る岡田卓也氏の「静かなる流通革命」の精神的支柱であった公器の理念は、日本の商人が長らく受け継いできた人や社会へのかかわり方の姿勢であり、江戸時代にまでさかのぼることができるといわれる。日本には、創業百年を超えて事業を継続する長寿企業が多い。日本が世界的な長寿企業大国であることと、日本の商人が長らく培ってきた、目先の利益を追うのではなく、中長期にわたる従業員や取引先や社会との健全な関係性を育むことを重視する精神のあいだには、何らかの関係があると思われる。
そして、この精神を引き継いできたイオンという企業が、中長期の展開のなかで国内最大の小売グループに上り詰めていることは、興味深い現象だといえる。
未来志向のもとでの『岡田卓也の時代』の読み方
『岡田卓也の時代』に描かれるのは、過去の歴史である。この書籍が扱うのは、第二次世界大戦後から流通革命へと至る時期の岡田屋とジャスコのビジネスモデルを巡る比較研究であり、そこに公器の理念が果たしていた役割の検討である。
しかし、この書籍を、過去の出来事の理解のために読むのか、そこからさらに新しい未来に向けた行動への示唆を読み取るかは、私たち読み手にゆだねられている。一般に書籍というものが示しているのは、開かれた可能性であり、その最終的な価値や意義は読み手との間接、あるいは直接の対話のなかで定まっていく。
では、一読者として、『岡田卓也の時代』から、何をどのように引き出していくか。私は、今回のワークショップを未来志向の学びの機会としたいと考えた。歴史と向き合い、過去についての理解を深めていくことも大切だが、そこから未来に向かう個人、組織、社会の歩みにつながる構想を引き出すことも欠かせない(図2)。この未来への挑戦への意欲を失ったとき、経営学という学問の社会における価値は間違いなく低下する。
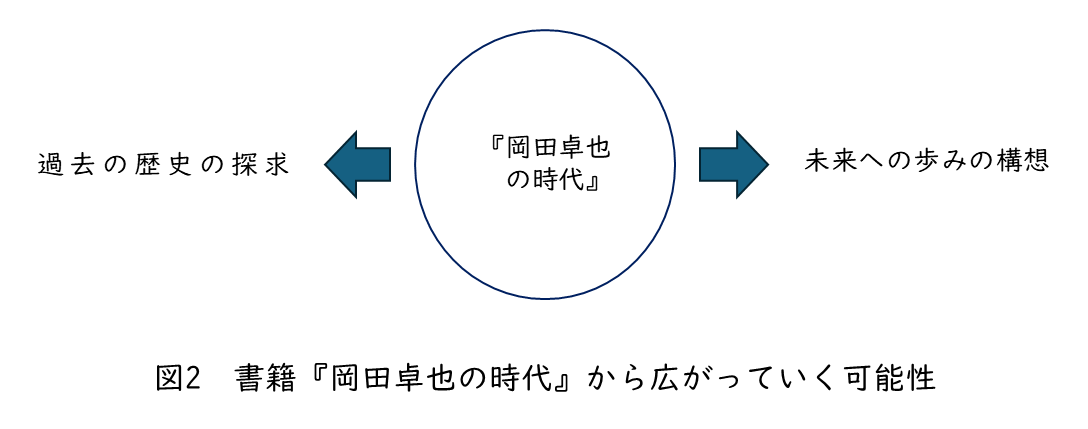
このように思いを巡らすなかで、私は今回のワークショップでは、『岡田卓也の時代』に込められている未来への歩みに向けたメッセージを、参加者の方々と石井淳蔵先生と共に読み解き、語り合いたいと考えた。そして思い当たったのが、第二の講演者として原丈人先生にご登壇いただくというアイデアである。
会社は誰のものか、そして何のために存在するか
原先生が提唱してきた「公益資本主義」。そこには、一握りの資本家に富が集中するのではなく、社会全体が豊かになる新しい資本主義のあり方が提示されている(原丈人著『「公益」資本主義:英米型資本主義の終焉』文春新書、2017年)。公益資本主義は、新自由主義という世界を席巻している株主資本主義に対するアンチテーゼであるとともに、日本の商人の思想である公器の理念との親和性の高い考え方である。現在、欧米などでは国や社会の分断が政治上の深刻な問題となっているが、早くから原先生は株主資本主義が持つ収奪経済的な性格が、社会の二極化を引き起こすことに警鐘を鳴らし、この問題に対する処方箋として公益資本主義を提唱してきた。
公益資本主義、そして公器の理念が向き合っているのは、会社は誰のものか、そして何のために存在するかという問いである。そして、これらの問いへの答えは、経営をどのように律するかというコーポレートガバナンスの問題へとつながっていく。
コーポレートガバナンスは、マーケティング論をはじめとする経営学の緒論の根幹にかかわる。なぜなら、事業を誰のどのような目的のために営むかという構想は、経営学の緒論が解明しようとする諸問題のゴール設定にかかわるからである。
現在、コーポレートガバナンスの背後にある主流派の考えは、株主利益の追求を最優先とする株主資本主義である。株主資本主義は、歴史のなかに登場した一つの経営思想であり、これを普遍の真理と見てよいかについては、議論の余地がある。
一方で、このトレンドは大きな潮流となっている。「会社の所有者は株主であり、経営の目的は利益を上げて株主に還元することだ」という考えが、世界中のMBAなどで教えられている経営学やマーケティング論、そしてそれらを支える研究の前提となって久しい。
こうした状況は、英米だけではなく、日本においても変わらない。確かに日本には、企業というのは社会からの預かり物であり、経営者や株主だけのものではないという考えが、人々のあいだにまだ残っている。伝統的な商人の思想に由来する公器の理念は、根絶やしにはなっていない。しかし、現代の大きなトレンドの一つである株主資本主義の影響力が強まっていけば、欧米の国々に見られる収奪的な経済システムと社会の分断の問題は、対岸の火事といえなくなっていく恐れがある。
失われたものを嘆くのではなく、次なる可能性に目を向ける
私たちが未来に向けて歩みを進めていく上では、大切に共有できる価値を守りながら、そのもとでの利益の増大を目指すという公器の理念、そして公益資本主義の考え方の重要性を再確認するべきである。利益の増大は企業経営における重要な目標ではあるが、この目標を追求していった結果、企業の事業活動を支える環境、すなわち地域や社会の健全な秩序を破壊してしまっては元も子もない。だからこそ、今回のワークショップでは、流通革命の時代とその帰結を振り返りながら、これからの企業経営は何を目指すべきなのか、そしてそこから生まれる未来について語り合いたいと思う。
私はそろそろ60歳になろうという年齢である。日本の高度経済成長期については、社会人として体験したわけではない。家族の暮らしぶりや大人たちから聞いていたことなどを振り返ると、私の幼少期の日本はまだ貧しく、「東洋の片隅の小さな国」などと語られていた。第二次世界大戦の敗戦から立ち直ろうとする小国だった日本。とはいえ、あの時代の日本は未来への希望に満ちた社会であったと思う。
ところが、私の青年期以降の35年ほどの日本は、「失われた10年」が「失われた20年」となり、「失われた30年」となっていく時代へと突入していった。しかし、この35年の日本は惰眠をむさぼっていたわけではない。一つの課題を克服すると次なる課題が出現するという、気を緩めることのできない日々を歩んできた。また「失われた」とはいっても、戦後の焼け野原のように、何もかもすべてを喪失してしまうことはなかった。
私たちが向き合わなければならないのは、失われたものを嘆くことに終始するのではなく、次なる未来に向けた歩みを、どのように構想するかという問題である。なぜなら、何かを得ることは、何かを失うことだからである。これは裏返すと、何かを失うことは、何かを得ているということである。この35年間に日本が多くを失ったとすれば、その裏返しとして多くの可能性を得ているはずである
そのなかで今、日本という国、そしてそこで活動を続ける企業は、二つの大きな問題への対応を迫られている。気になる一つの動きは、米国発のトランプ・ショックであり、もう一つの問題は、日本で進行している少子高齢化である。日本は引き続き大きな問題に直面しているわけだが、裏返せば、そこに日本の可能性が潜在していると考えることもできる。
だからこそ、石井先生と原先生の講演を踏まえて、ご参加いただいた皆さまと共に、経営哲学の問題に向き合い、公器の理念から生まれる企業や社会の可能性について語り合い、認識を広げ、掘り下げていきたいと思う。さあ、幕が上がります。
